この記事は2025年9月16日にリニューアルしました。
業務効率化・コスト削減・環境対策を実現する次世代モビリティ戦略
2023年7月1日の道路交通法改正により、「特定小型原動機付自転車」という新たな車両区分が創設され、16歳以上であれば運転免許不要で電動キックボードを利用できるようになりました。
この法改正は、法人にとっても電動キックボードを事業活用する大きな追い風となっています。
業務効率化、コスト削減、そしてCO₂排出量削減といった企業経営に直結するメリットは多く、実際にトヨタ九州宮田工場では大規模導入により、従業員の移動時間が大幅に短縮されたという成果が報告されています。
この記事では、法人向け電動キックボードの導入メリットから、具体的な導入形態の比較、必須となる安全対策、そして活用できる可能性のある補助金・助成金の探し方まで、導入を成功させるために必要な情報を総合的に解説します。
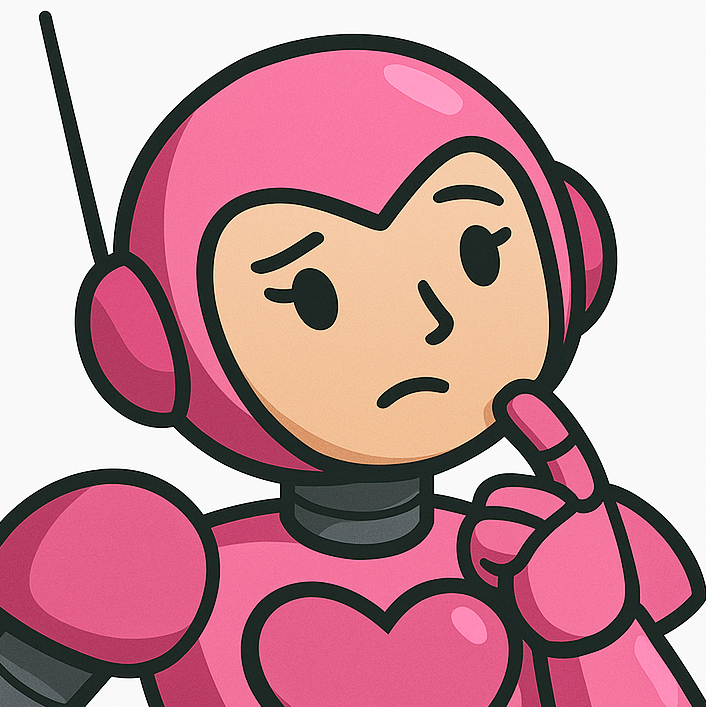
電動キックボードを法人で導入するメリットって本当にあるの?
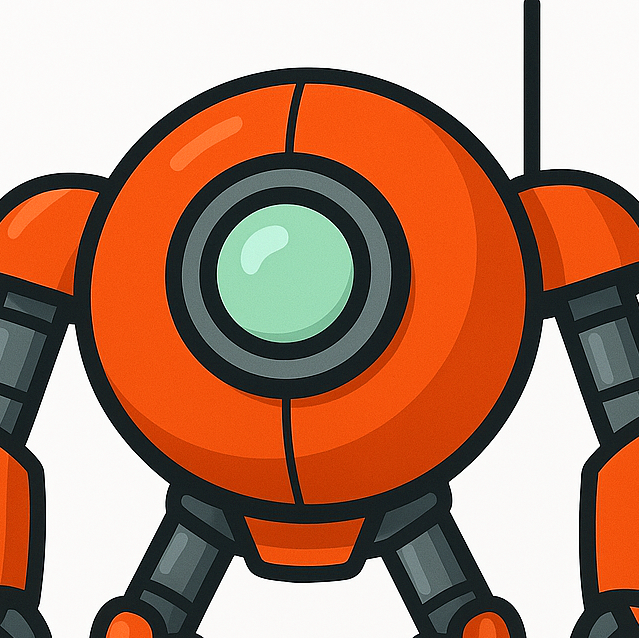
はい!実際にトヨタ九州や西日本シティ銀行など、多くの企業で導入効果が報告されています。業務効率化だけでなく、環境対策やコスト削減にも貢献する可能性を秘めています。
法改正による電動キックボードの新ルールと企業への影響
2023年7月1日施行の道路交通法改正の詳細
2023年7月1日に施行された改正道路交通法により、電動キックボードに「特定小型原動機付自転車」という新たな区分が創設されました。
これにより、企業での電動キックボード導入が、より現実的な選択肢となっています。
特定小型原動機付自転車の主な基準
- 車体の大きさ:長さ190cm以下、幅60cm以下
- 原動機:定格出力0.60kW以下の電動機
- 最高速度:時速20km以下
- 走行中の速度設定変更ができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構であること
- 最高速度表示灯の装備
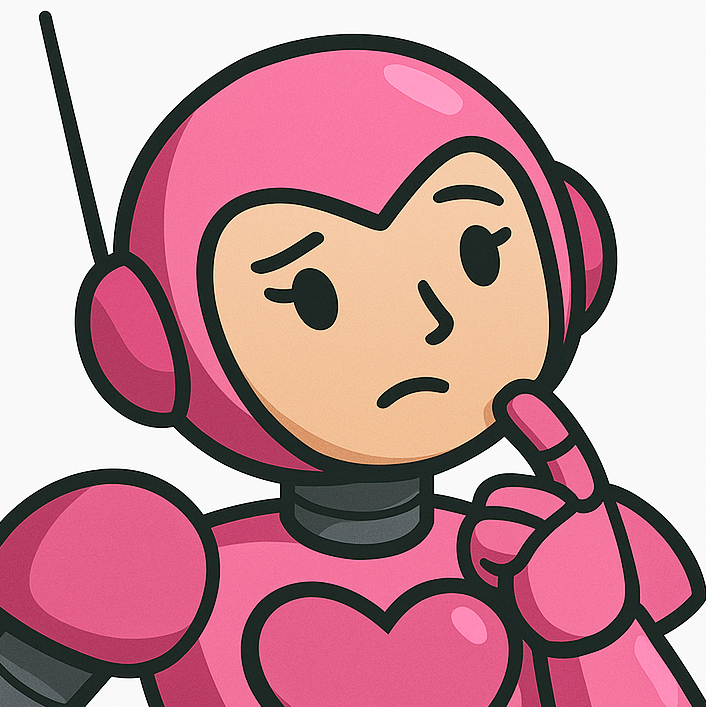
16歳以上なら誰でも乗れるってことですか?
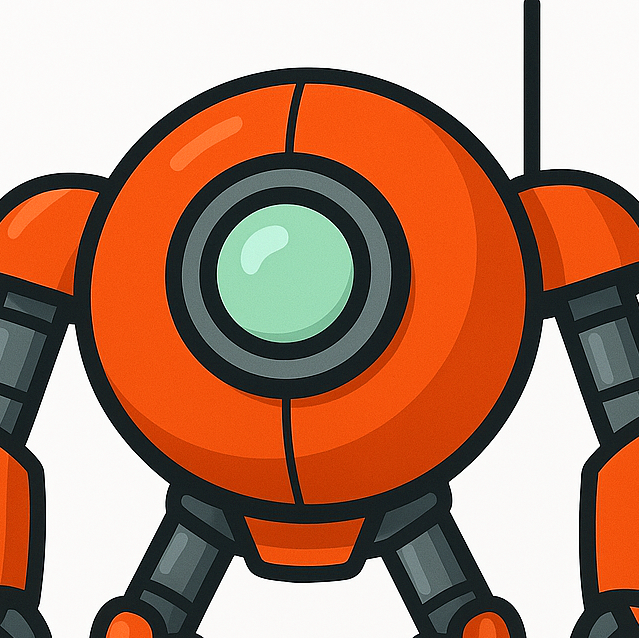
はい、その通りです。特定小型原動機付自転車の基準を満たした電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許が不要です。ただし、自賠責保険の加入とナンバープレートの取り付けは法律で義務付けられています。
企業導入における法的要件
法人が電動キックボードを導入する際は、以下の要件を満たす必要があります。
企業導入における法的要件
- 自賠責保険の加入: 公道走行には自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務です。
- ナンバープレートの取得・表示: 市区町村の役所でナンバープレートを取得し、車体に表示する義務があります。
- 保安基準への適合: 道路運送車両法の保安基準(前照灯、警音器、尾灯など)に適合していることが必須です。
- ヘルメット着用: 法律上は努力義務ですが、従業員の安全を確保し、企業の安全配慮義務を果たすため、社内ルールで着用を義務化することを強く推奨します。
法人向け電動キックボード導入の具体的メリット

業務効率化の実現
- 移動時間の短縮: 広大な工場敷地内や、駐車場から目的地まで距離がある事業所などで特に効果を発揮します。駐車場を探す時間や交通渋滞を回避できるため、営業活動でも有効です。
- アクセス性の向上: 駅から事業所までの「ラストワンマイル」を解決します。狭い道や一方通行路でもスムーズに移動でき、小回りが利きます。
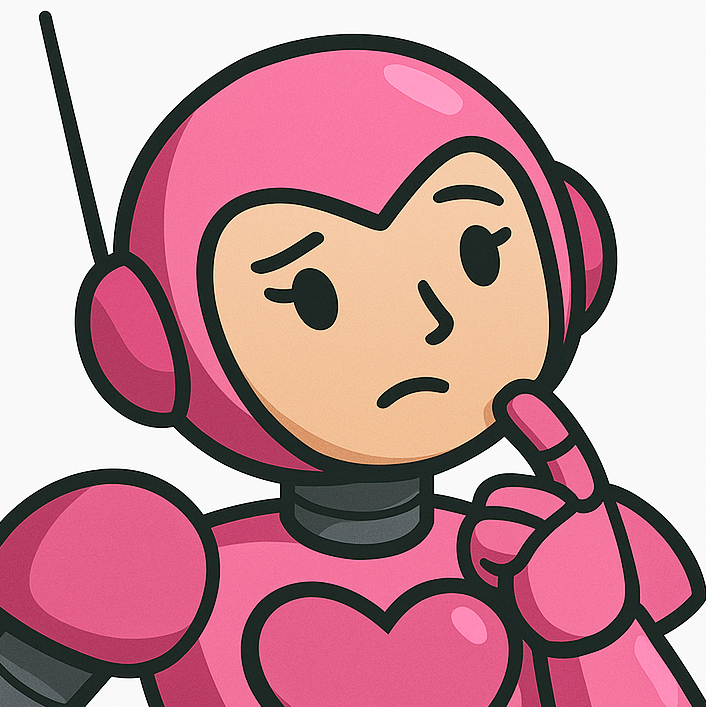
実際の業務でどれくらい効率が上がるんですか?
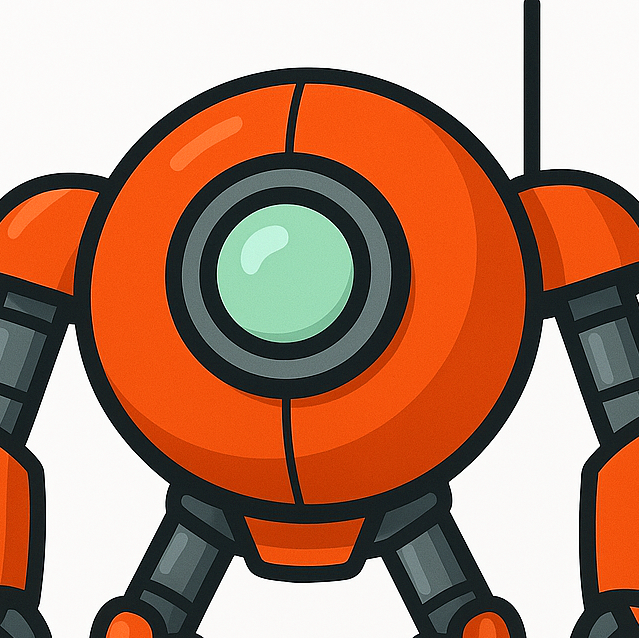
例えばトヨタ九州の事例では、広い工場敷地内での移動時間が大幅に短縮され、その時間を本来の作業に充てることで生産性向上につながったと報じられています。
コスト削減効果

- 燃料費の削減: 1回の充電にかかる電気代は数十円程度(※)と非常に安価で、ガソリン車と比較して燃料費を大幅に削減できます。
※バッテリー容量や電力料金単価により変動します。 - 維持費の軽減: 特定小型原動機付自転車は車検が不要です。また、構造がシンプルなため、自動車に比べてメンテナンス費用も安価に抑えられます。駐車場代が不要になるケースも多いでしょう。
環境対策・企業イメージ向上
- CO₂排出削減: 走行時にCO₂を排出しないため、企業の脱炭素目標の達成やSDGsへの取り組みとして、社外へ具体的にアピールできます。
- 企業イメージの向上: 環境配慮や先進的な取り組みを行う企業として、ブランディング向上や人材獲得にも好影響が期待できます。
成功事例から見る導入効果



導入形態とコスト比較
導入形態には大きく分けて「購入」「リース」「シェアリング」の3つがあります。
| 導入形態 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |
|---|---|---|---|
| 購入 | 長期的な総コストを抑えられる可能性がある、資産計上できる、自由にカスタマイズ可能 | 初期費用が高い、維持管理の手間がかかる、故障・盗難リスクを自社で負う | 長期的に多数の車両を利用する企業 |
| リース | 初期費用を抑えられる、メンテナンス費用が含まれるプランが多い、費用を平準化できる | 長期的な総コストは購入より割高になる傾向、契約期間の縛りがある | 中期的な利用、予算管理をシンプルにしたい企業 |
| シェアリング | 初期費用ゼロ、必要な時だけ利用できる、メンテナンス不要 | 1回あたりの利用料は割高、使いたい時に車両がない可能性がある | 利用頻度が低い、まずは試験的に導入したい企業 |
【重要】コストシミュレーションについて
ウェブサイトなどで見られるコスト比較は、あくまで特定の条件下での一例です。
車両本体価格、リース料率、シェアサービスの料金プランは常に変動します。
導入を検討する際は、必ず複数の事業者から自社の利用状況に合わせた最新の見積もりを取得し、比較検討してください。
安全対策とリスク管理
事故発生は企業の信頼を大きく損うリスクとなります。
導入にあたっては、万全の安全対策が不可欠です。
- 必要な保険の種類
- 自賠責保険(必須): 対人賠償を確保するための強制保険です。必ず加入してください。
- 任意保険(強く推奨): 自賠責保険だけでは補償が不十分な場合に備え、対人・対物賠償の上乗せ、運転者自身の傷害、車両の盗難などをカバーする任意保険への加入を強く推奨します。
- 安全教育プログラムの実施
従業員に対して、以下の内容を含む安全講習を必ず実施してください。- 道路交通法などの関連法規の遵守
- 安全な走行方法(一時停止、手信号、危険予測など)
- 日常的な点検・メンテナンス方法
- 事故発生時の対応手順
- 社内安全ルールの策定と周知徹底
- ヘルメット着用の義務化
- 社内独自の最高速度制限(例:敷地内は時速10km以下など)
- 走行禁止場所(雨天時、夜間、特定の道路など)の明確化
- 定期的な点検の実施義務
導入成功のポイント
- 導入目的の明確化
「移動時間を〇%削減する」「燃料費を年間〇〇円削減する」など、具体的な数値目標を設定することで、導入効果を測定しやすくなります。 - 充電ステーションの設置
従業員が利用しやすい場所に充電場所を確保します。基本的には既存の100Vコンセントで充電可能ですが、複数台を同時に充電する場合は、安全のために電源工事や専用設備の設置が必要になることもあります。
補助金・助成金の活用【最新情報の確認が必須】
電動キックボードの導入には、国や自治体の補助金・助成金を活用できる可能性があります。
ただし、これらの制度は年度ごとに内容が大きく変わるうえ、公募期間が限られており、予算に達し次第終了することがほとんどです。
「2025年最新版」として最も重要なことは、「必ず公式情報を自分で確認する」ことです。
情報の探し方
情報の探し方
- 国の制度: 環境省のウェブサイトなどを確認します。 (過去の参考例)「商用車等の電動化促進事業」などで、電動バイク等が対象に含まれるケースがありました。
- 自治体の制度: 事業所が所在する「都道府県名 市区町村名 EV 補助金」といったキーワードで検索し、自治体の公式サイトを確認します。 (過去の参考例)東京都や神戸市などで、電動バイク等の購入に対する補助金制度が実施された実績があります。


申請のポイント
- 公募期間を厳守する
- 申請要件(対象車両、対象事業者など)を熟読する
- 必要書類を不備なく準備する
製品選定のポイントと具体例

法人利用では、耐久性、安全性、メンテナンス性が重要になります。
選定のポイント
- 耐久性と耐荷重: 業務用として毎日使うことを想定し、頑頑なフレームやパンクしにくいタイヤを採用したモデルを選びましょう。
- バッテリー性能: 1回の充電での走行距離が、想定する業務利用の範囲をカバーできるか確認します。バッテリーが着脱式だと、室内で充電できて便利です。
- 安全性: 「性能等確認済シール」が貼付された、国の保安基準を満たした車両を選びましょう。ブレーキ性能やライトの明るさも重要です。
【製品例1】COSWHEEL MIRAI T Lite
この商品を詳しく知りたい方はこちら。
【製品例2】AINOHOT S07自賠責保険
この商品を詳しく知りたい方はこちら。
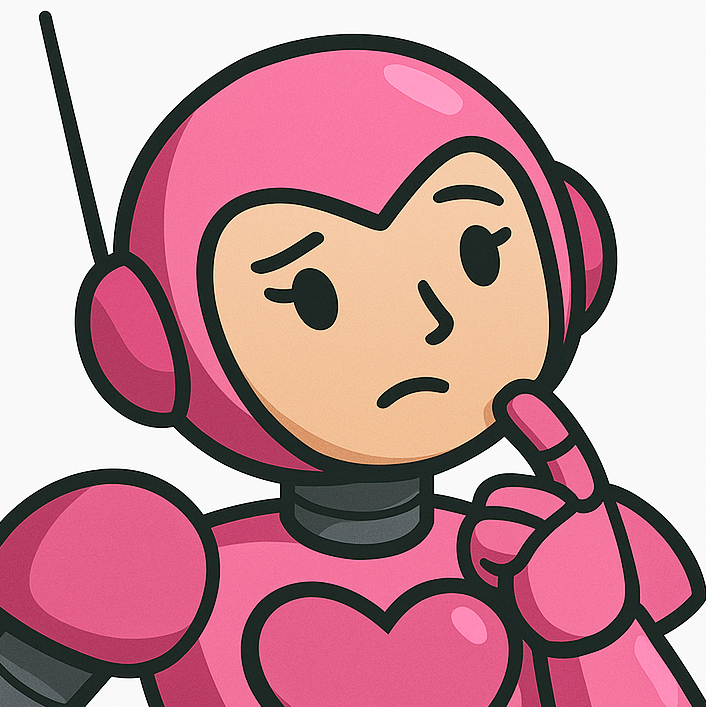
法人向けにはどちらがおすすめですか?
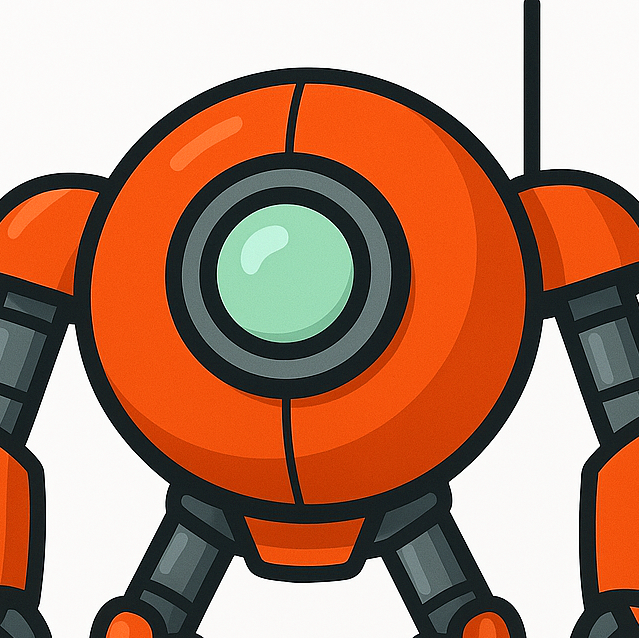
日常業務でハードに使うなら耐久性の高いCOSWHEEL、まずはコストを抑えて試したいならAINOHOTが選択肢になります。利用頻度、走行距離、予算に応じて最適な一台を選んでください。
よくある質問(FAQ)
- Q法人向け電動キックボード導入の初期費用はどれくらいかかりますか?
- A
購入の場合、1台あたり8万円~20万円程度が目安です。
これに加えて、自賠責保険料(年間7,000円台~、契約期間により変動)、ナンバープレート取得費用(数百円程度)が別途必要です。
- Q安全面で特に注意すべき点は何ですか?
- A
「保険加入」「安全教育」「社内ルールの徹底」の3点が最も重要です。
特に、従業員の命を守るヘルメット着用は、努力義務であっても社内では必ず義務化しましょう。
- Q充電設備の設置に費用はかかりますか?
- A
基本的には既存の100Vコンセントを利用できますが、複数台を同時充電する場合や屋外に設置する場合は、1基あたり5万円~20万円程度の専用充電スタンドや電源工事が必要になることがあります。
- Q税制上のメリットはありますか?
- A
リースで導入する場合、リース料を経費として計上できます。
購入の場合は減価償却資産として処理します。
環境関連設備として税制優遇の対象となる可能性もありますので、詳細は顧問税理士にご確認ください。
- Q雨天時の使用は可能ですか?
- A
多くの製品は防水性能を備えていますが、安全のため雨天時の使用は推奨されません。
路面が滑りやすく、ブレーキ性能も低下するため、社内ルールで雨天時の使用を禁止することをお勧めします。
まとめ
法人向け電動キックボードの導入は、法改正を追い風に、多くの企業にとって現実的かつ有効な経営戦略となりつつあります。
導入による主要メリット
- 業務効率化: 移動時間を短縮し、生産性を向上。
- コスト削減: 燃料費や維持費を大幅に削減。
- 環境対策: CO₂排出ゼロで、企業のSDGsへの貢献をアピール。
成功への鍵
- 導入目的を明確に設定する。
- 利用状況に合った導入形態(購入・リース・シェア)を選択する。
- 何よりも安全を最優先し、保険加入・安全教育・ルール策定を徹底する。
- 補助金・助成金は、必ず国や自治体の公式サイトで最新情報を確認する。。
トヨタ九州をはじめとする多くの企業で導入効果が報告されており、電動キックボードは業種や企業規模を問わず活用できる次世代モビリティです。
この記事を参考に、自社に最適な導入プランを策定し、持続可能な企業経営と業務効率化の両立を実現してください。



